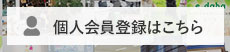障害者の過去をたどる旅~「医療の負の歴史」ロボトミー手術はなぜもてはやされたのか
暮らし
出典:Photo by Natasha Connell on Unsplash
クライマックスで主人公がロボトミー手術を受けさせられ廃人となってしまう、映画「カッコーの巣の上で」。
作中での禍々しい演出からもわかるように、現在ではロボトミー手術は「精神医療の負の歴史」という扱いです。
しかし、ロボトミー手術が考案された時代の精神医療は、私たちが想像もできないほどお粗末な状況にあり「トンデモ治療」といい切れなかったことは、知っていますか?
悲惨だった20世紀初頭の精神医療
最初のロボトミー手術がおこなわれたのは20世紀初頭です。当時の精神医療のレベルは、現在の医療とくらべると、0に等しいものでした。
なぜならその当時、精神疾患に対し効果的治療がない状態だったからです。それにもかかわらず、精神科病院に入院する患者は増える一方でした。
精神科医たちは多くの患者に対してなすすべがなく、絶望していました。そして、わずかに試みられていた治療法も、患者を危険にさらすものしかありませんでした。
当時の代表的な治療法として、インシュリン・ショック療法や電気ショック療法があります。
インシュリン・ショック療法とは、インシュリンを患者に継続的に注射し、患者を強制的に低血糖状態にし、昏睡状態にさせる手法です。昏睡状態にさせた後は、グルコースを注射して覚醒させます。
この療法は当時、精神的混乱を軽減できるとされていましたが「もし昏睡から覚めなかったらどうするのだろう?」と疑問に思う人もいるでしょうし、実際そうした事故はつきものでした。
電気ショック療法については「ひと昔前の精神病の治療方法」といったイメージを、持っている人もいるでしょう。
頭部に電流を流し、けいれんを意図的に起こさせることで「統合失調症や重度のうつ病患者の症状軽減に効果がある」とされていました。
しかし、電気ショック療法を受ける患者は拷問のような苦痛を感じ、中にはけいれんを起こし過ぎて背骨を折った患者が居たという記録があります。
仮に精神症状が軽快しても、重症を負う可能性がある治療を、率先して受けたいとは思えませんよね?
さて、今度は当時の精神病院の環境について見てみましょう。20世紀初頭のアメリカの州立精神病院は、どこも患者でいっぱいでした。
病院の環境は最悪で、看護職からの患者への暴力やネグレクトなどが日常茶飯事なうえ、患者に対する殺人まで起きていました。そればかりか、患者同士の殺人も頻発していたのです。
つまり、精神病院はこの世の地獄も同然でした。
こうした状況下で多くの精神科医が「何か画期的な治療方法はないものか?」と、懊悩していたことは、想像に難くありません。
神経科医エガス・モニスのひらめき
1935年、ロンドンで開かれた神経学会で、イェール大学の生理学者たちが、チンパンジーを用いた研究結果を発表しました。
彼らは2匹のチンパンジーに棒を使った食べ物の取り方を訓練した後、それぞれの脳の前頭葉を切除する手術をおこないました。
すると2匹とも食べ物の取り方を忘れてしまったのですが、うち1匹にある変化があらわれたのです。
ベッキーと呼ばれたそのチンパンジーは怒りっぽい性格で、気に食わないことがあると自分の糞を学者に投げつけるような、激しい気性の持ち主でした。
しかし、手術をしたあとは別人のように穏やかになったのです。
彼らは前頭葉が記憶をつかさどる部位だと確信したと同時に、前頭葉を手術することで、不安障害を治せるのではないかと発表したのでした。
この発表に対し、強い興味を持った医師がいました。それがポルトガルの神経科医である、エガス・モニスです。
モニスは「手術を人間にも応用し、前頭葉と視床の連絡繊維を切断して、不安障害を治療できないだろうか?」と考えました。
実は、彼は不安症状に悩まされる患者を多く抱えており、効果的な治療を模索し続けていたのです。
実際に手術してくれる外科医としてペドロ・アルメイダ・リマを起用したモニスは、何と死体を使って1度だけ手術の練習をしただけで、最初の手術をどの患者におこなうかを考えはじめました。
最初の被験者としてモニスが選んだのは、精神障害者施設に収容されていた女性患者です。彼女は生活に支障をきたすレベルで、不安障害と妄想に苦しめられていました。
1935年11月、リマは患者の頭蓋骨の両側に穴をあけ、そこからティースプーン1/2杯のアルコールを前頭葉に注入。手術は30分ほどで終わり、数時間後には女性は簡単なやりとりができるまでに回復したのです。
モニスは「患者は手術前よりも落ち着いた状態になり、不安障害と妄想はなくなっていた。女性は手術により治癒した」と考えたのです。
最初は前頭葉の白質をアルコールで壊死させていたモニスとリマでしたが、やがて細い管の器具を前頭葉に挿入し、白質部分を切除する新しい手法を編み出しました。
この手術をギリシャ語の「白(leuko)」と「切除(tome)」にちなんで、彼らはロイコトミーと呼びました。尚、現在でもヨーロッパでは「ロボトミー」ではなく「ロイコトミー」と呼ぶ専門家が大勢います。
最初の手術から3か月ほどで、モニスらの手術件数は20件を超えました。そこでモニスは手術を受けた患者についての実績をまとめた論文を発表します。
その論文によれば7人の患者が治癒し、7人は精神症状が大幅に改善され、残る6人には変化なし。結果を見れば、誰もが素晴らしい治療方法だと賞賛することでしょう。
しかし、モニスの地元ポルトガルでは奇妙な現象が起こります。これまでモニスに患者を紹介していた精神科医が紹介をしなくなっていき、最終的にポルトガルではロイコトミーは禁止されてしまうのです。
モニスは「手術による悪影響はない」と話していましたが、実は彼がおこなった手術の患者の予後は、総じて惨憺たるものだったのです。
患者たちは嘔吐や下痢、異常な食欲、そして今がいつで自分が誰なのかわからないという見当識障害に悩まされます。しかしこうした症状についても、モニスは「一時的なもの」と楽観視したのです。
モニスは最終的にノーベル賞を受賞。モニスの受賞からおよそ40年でロイコトミーは4万件も実施され、そのうちの半分はアメリカでの手術でした。
アメリカで手術の人気が爆発的に高まった裏には、ウォルター・フリーマンという精神科医の、狂信的ともいえる熱意があったことを知る人は、どのくらいいるでしょうか。
ウォルター・フリーマンによるロボトミー手術の拡大
ウォルター・フリーマンは両親と父方の祖父が医師という家族に生まれました。
特にフリーマンの父方の祖父ウィリアム・キーンは、アメリカ初の脳腫瘍摘出手術の執刀医であり、その他開胸した状態での心臓マッサージに成功するなど多くの偉業を成し遂げた、いわば「エリート中のエリート」。
祖父を尊敬していたフリーマンでしたが、同時に偉大な祖父に対するコンプレックスも感じていました。そのコンプレックスが、フリーマンをロボトミー手術の普及に駆り立てたのではないかという意見もあります。
彼はかねてから「重度の精神疾患を抱える患者の脳には、構造的な差異がある」という仮説を信じており、エガス・モニスの発表した論文はまさに福音で、自分でも手術を手がけてみることにしたのです。
フリーマンの最初の患者は、アリス・ハマットという60代の主婦でした。彼女は不眠症や不安症だけでなく、時にはヒステリックに笑い出したり泣きたりして、フリーマンや彼女の夫を悩ませていました。
ハマット自身は手術について乗り気ではなかったのですが、夫が手術を受けることを熱心に薦め、根負けした彼女は手術を受けることを決意。
1936年9月、ハマットの手術が行われました。執刀したのはジェームズ・ワッツという医師で、ワッツは頭蓋骨に穴をあけ、ナイフを脳の中に差し込み、前頭葉を6か所切り離すことに成功しました。
彼女は穏やかな表情で目を覚ました後「不安を忘れてしまったみたい」と話しましたが、しばらくして様子が不穏になり始めます。
言葉がつっかえるようになり、単語の綴りを忘れ、やがて会話が成立しなくなったのです。しかし、ハマットは精神的には穏やかになり、不眠症もなくなっていました。
ハマットの手術の17日後、フリーマンは症例を医学界で報告。彼はワッツが執刀した手術を後にギリシア語の「葉(lobos)」と「切除(tome)」から由来する「ロボトミー」と呼びました。
彼は得意げに患者は治癒したと話しましたが、中には「治癒」という言葉に納得できない医師もいました。
しかしその後もフリーマンとワッツは複数の患者に手術をおこない、その結果を神経科医や精神科医の前で説明しました。
「患者全員に精神症状の改善があった」「患者は穏やかになり、不満を持たず、幻覚なども無くなった」と盛んに喧伝するのですが、医師たちは多くの疑問を抱きます。
「手術の時に脳血管を傷つけるのではないか」「短期間の経過を見ただけで『治癒した』と結論を出すのは、性急すぎるでは?」……実はこのような疑問は、フリーマンの痛いところを突いていました。
何故なら彼は手術で生じた副作用を、一切説明していませんでした。副作用どころか、脳に深刻な損傷が残った患者もいたのです。
隠された「副作用」と簡易化した手術「アイスピック・ロボトミー」
患者の脳に損傷が残ったのは、もちろんロボトミー手術が原因でした。手術中にあやまって大動脈を切断してしまったのです。
加えて、手術後に一旦精神状態が安定したものの、再び症状が悪化したために再手術となった患者も複数いました。
そのうち3人が心臓発作や脳出血を起こして命を落とし、1人は脳の機能障害を起こし、生涯介護施設から出られなくなったことも、フリーマンは隠したのです。
しかし、こうした事情を知らない米国の医学雑誌は「ロボトミー手術は理にかなったもの」と評価。
1937年6月にはニューヨーク・タイムズ紙の一面で「獰猛な野生動物のような精神病患者が数時間で穏やかに落ち着く、魔法のような手術」とロボトミー手術を絶賛する記事が掲載されました。
フリーマンとワッツ、そして2人から指導を受けた医師によるロボトミー手術は、1951年までに1万8千件を超えました。これだけの手術をおこなえたのは、フリーマンが手術の手法を簡易化したからです。
彼は、まず手術は診察室でおこなうことにしました。全身麻酔を使わず、電気ショックで患者を失神させてから手術することにし、頭蓋骨にドリルで穴をあけることもやめてしまいました。
フリーマンは何と、眼窩上部の内側にアイスピックを差し込み、小さなハンマーでアイスピックをコツコツとたたいて前頭葉にアイスピックを到達させ、脳を切り取るという手法を試み始めたのです。
新しい手法により、手術時間は10分以下になりました。しかしワッツには、この新しい手法は知らされませんでした。
ワッツがフリーマンの診察室に立ち寄ったとき、フリーマンはまさに「執刀中」でした。ワッツは患者であるマリー・イヨネスコの眼窩に刺さっているアイスピックを見て仰天し、黙り込んだといいます。
この新しい手法は「脳の手術は、脳を見ながら慎重に行うべき」がモットーのワッツにとって、とても受け入れられませんでした。これをきっかけに、フリーマンとワッツは袂を分かちます。
相棒を失ったものの、新しい手術方法に自信満々なフリーマンは全米を回って、この「アイスピック・ロボトミー」を実演しました。果てはカナダや南米の病院にも足を運び、ロボトミー手術は誰もが知る治療方法になりました。
確かに多くの患者は、手術後一様におとなしく、穏やかになったように見えました。しかし同時に、多くの患者は「自分に対しても他人に対しても興味を失った状態」に陥ったのです。はっきりいってしまうと、人格荒廃です。
そうした患者のなかには、人前でいきなり全裸になったり、他人の皿から食事を奪って食べたりするものまでいました。
しかしフリーマンにとっては、患者の深刻な状況は大したことではなく「手術前より穏やかになった」ことが、重要だったのです。
ロボトミー手術の犠牲者としてもっとも有名なのは、アメリカ大統領ジョン・F・ケネディの妹である、ローズマリー・ケネディでしょう。
彼女は軽度の知的障害がありましたが、ひとりで海外旅行をしたり、ヨットレースに参加するなど活発な女性でした。
しかし成長するにつれ上手く怒りをコントロールできなくなったローズマリーは、自宅で大声を上げたり暴れたりといった問題行動を繰り返すようになってしまったのです。
「ローズマリーは、いつかケネディ家の政治活動を脅かすかも知れない」と懸念を抱いた彼女の父ジョセフは、秘密裏にロボトミー手術を受けさせることを決断しました。
その結果、ローズマリーは手術が終わったあとは自力で歩くこともできなくなりました。
ジョセフは娘を私立病院に入院させて手厚くリハビリを受けさせたので、数か月後に歩くことはできるようにはなりました。
しかし、手術以前の記憶があいまいになり、身の回りのことは何もできなくなりました。2005年に亡くなるまで、彼女は人生の大部分を精神病院で孤独に過ごしたのです。
手術を受けた患者の悲惨な末路が伝わりはじめたことから、ロボトミー手術に「医療的サディズムだ」などの多くの批判的な意見が出るようになりました。
そして抗精神病薬の発見と開発が、ロボトミー手術にとどめを刺したのです。
1952年、フランスの精神科医ジャン・ドレーが、クロルプロマジンが躁病及び統合失調症の錯乱や幻覚を改善することを発見。
1954年にはアメリカでクロルプロマジンが治療薬として承認され、その後「ソラジン」という製品名で販開始。
さらに1955年には抗うつ薬のトフラニールの販売が始まり、1957年にはベルギーの薬理学者ポール・ヤンセンが、現在でも使用されているハロペリドールを開発。
次々に開発される向精神薬により、ロボトミー手術は淘汰されていったのです。
ロボトミー手術での治療と向精神薬を用いた治療の大きな違いは「不可逆性の有無」でしょう。
もしもある向精神薬が患者に合わなければ、投薬を中止して別の向精神薬を試すことができます。しかし、ロボトミー手術の場合はそうはいきません。
脳を1度外科手術で切り取ってしまったら、現代の技術をもってしても、元に戻すことはできないのです。
現在、エガス・モニスとウォルター・フリーマンに対する評価は割れています。ロボトミー手術により深刻な後遺症が残った家族と遺族たちは、モニスのノーベル賞を取り上げるべきだと訴え続けています。
最後に、個人的な所感を書いていきます。私は、このロボトミー手術がもてはやされたのは、いくつかの要因が重なった結果によるものだと考えています。
まず、当時の精神医学は治療法に恵まれなかったことは最初にお話ししましたが、閉塞感と焦りで、ほぼ全員がある種の思考停止状態だったと推察します。
治療効果が不透明な治療法しかない中、華々しく「この治療法で患者の不安感が無くなった!」と論文を引っ提げたモニスやフリーマンが登場。
閉塞感に苦しんでいた医学界は新しい治療法に安易に飛びついてしまいますが、実は発表した医師が治療によるデメリットを隠していたことを知りませんでした。
また、モニスもフリーマンも不可逆的な治療であるにも関わらず、術後の経過を長期間観察するなどの検証を十分におこなっていなかったことも問題でしょう。
しかし、ロボトミー手術を執刀したのはモニスとフリーマンだけではありません。大勢の医師が執刀し術後の経過を観察していたはずなのに、長い間「この手術は危険だ」と誰も口火を切らなかったのです。
これはなぜでしょうか?
あまり考えたくないのですが、フリーマンが「以前よりは穏やかになったのだから」と副作用を軽視したように、多くの医師たちも「まあ、暴れたりしなくなったし」と、見て見ぬふりを決め込んだのかも知れません。
患者の無気力ぶりを見て見ぬふりをしたことには、当時の人権意識の低さも有ったでしょう。特に精神病者への偏見は今よりも相当ひどく、医師も無意識に患者を軽視していた可能性もあると考えます。
実に奇妙なことに、ロボトミー手術の多くが女性に施されました。カナダのある州では、手術を受けた患者のうち74%が女性だというデータもあります。
女性はより弱い立場のため「頭のおかしい面倒な女はみんな手術してしまえ」と軽んじられたのではないか?と疑ってしまいます。
「貧弱な治療方法しかない状況」「検証が十分おこなわれていない治療」「軽視された患者の人権」などの条件が重なったことから、ロボトミー手術は精神医療の代表として、長期に渡って君臨してしまったのではないでしょうか。
ロボトミー手術の悲劇を無駄にしないためにも、私たちはもっと医療のありかたに関心を持たなくてはならないのかも知れません。
患者本人のためにならず、不可逆性の高い医療行為を、絶対に許してはならないのです。
参考文献
ポール・A・オフィット著 大澤基保監修 関谷冬華訳 「禍いの科学 正義が愚行に変わるとき」日経ナショナルジオグラフィック
NHK「フランケンシュタインの誘惑」制作班著 「闇に魅入られた科学者たち 人体実験は何を生んだのか」NHK出版
【精神科医療について】
https://www.mhlw.go.jp/index.html
オンラインサロン「障害者ドットコム コミュニティ」に参加しませんか?
月々990円(障害のある方は550円)の支援で、障害者ドットコムをサポートしませんか。
詳細はこちら
https://community.camp-fire.jp/projects/view/544022